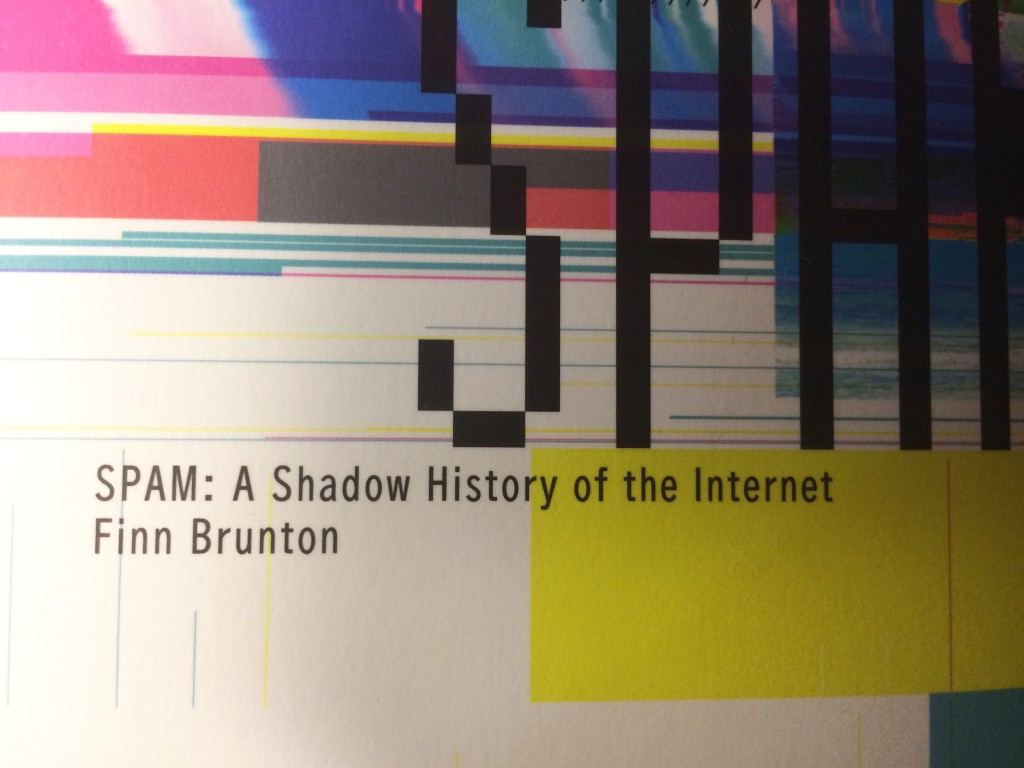新しいメディアが登場すると、理想を仮託しがちだ。とくにインターネットは、公共性を支えるプラットフォームとして期待される傾向があったというのは、社会学者の佐藤俊樹氏が指摘するとおりである(『社会は情報化の夢を見る』)。しかし日常生活においては、インターネットでは公共性に対して関心は払われず、「価値のない」情報ばかりが目につく。その象徴がスパム(迷惑メール)である。そこで、「注目の搾取」という観点から、スパムの歴史に注目したい。
フィン・ブラントン『スパム[spam]〜インターネットのダークサイド』(河出書房新社刊)
『スパム[spam]〜インターネットのダークサイド』は、スパムの歴史と遷移を克明に描くだけでなく、ネットの「闇」から逆照射する形で、「光」としてのコミュニティや統治(ガバナンス)のあり方を示唆し、そして、覗き込む私たちを見返す深淵のような著作である。
著者のフィン・ブラントン氏は、スパムを「情報テクノロジー基盤を利用して、現に集積している人間の注目を搾取すること」と位置づけている。そのため、迷惑メールだけでなく、検索結果に表示されるジャンクなウェブサイト、SNS上で友人の投稿と混じった宣伝や自分を大きく見せるためにフォロワー数を水増しする行為なども、本書の射程に含まれる。
テクノロジーのドラマ
スパムには様々な形態があるが、本書は、その歴史を三幕に分ける。
第一幕は、1970年代初頭から1995年である。最初に登場する人物は、ARPANETなどコンピュータ・ネットワークの礎を築いたウィザード(魔法使い)たちである。ARPANETは米国国防省における研究の一端であったため、ウィザードたちは、高度の技能をもち、お互いに顔見知りで信用を分かちあっていた。そのため、議論を通じた「規範」形成によってスパムに対処した。Usenetの登場で大学院生などが姿を現すと、ニュービー(新参者)にも規範が伝授された。しかし、インターネットの民間移行とともにウェブの時代が到来すると、多数の人々が舞台にのぼることになった。規範は共有されにくくなり、スパムの爆発を招いたのである。
(なお、「スパム」は、もともと缶詰の商品名であるが、コメディ番組『空飛ぶモンティ・パイソン』のなかで、反復してイライラさせるものを指す冗談として使われた。そのため、同番組を愛するギークばかりだったコンピュータ・ネットワーク初期のコミュニティにおいて、スラングとして使われはじめたとされている。)
続く第二幕は、1995年から2003年だ。ウェブにおける商業活動の活発化とドットコムバブルの崩壊を経て、いよいよ多くの人が加わるようになった。スパム文学とも呼べるような(例えば、「裕福な亡命一家がジンバブエから脱出しようとしているので資金移動を手伝ってほしい…」「フランスの航空機事故で亡くなった方の親類探しであなたの名前が…」など、冷静にみればなかなかに可笑しい)変奏が数多く生み出されたのもこの時期だ。
そうしてとうとう、スパムは「法」によって規制されるに至った。迷惑メール対策としてCAN-SPAM法が米国で成立したのである。もっとも、規制の漸進的歩みに対抗してスパムの技術革新は進み、リンクスパム、コメントスパム、スパムブログなどメール以外の技術的な足場を得て、検索エンジンのアルゴリズムを逆手にとるようになった。
2003年から現在の第三幕では、スパム関連産業に劇的な変化が起きる。ビッグデータ分析によりアルゴリズムの精度が向上し、スパムフィルタという強力な「アーキテクチャ」(ローレンス・レッシグ『CODE』)によって、多くのスパムが駆逐されたのである。ところが、結果としてスパムはより闇を深めることになった。自動化システムと分散コンピュータが開発され、エストニア政府へのサイバー攻撃など軍事的応用にもつながるような犯罪インフラが構築されている。
このようなテクノロジーのドラマを、本書は生々しく描く。厚顔無恥な慮外者による告知、受け手の迷惑顔、鷹揚なシステム管理者、プロセスクイーン(自治厨)の苛立ち、ヴィジランティ(ネット自警団)によるスパマーへの嫌がらせ、スパム業者同士の密かで大規模な情報共有、テクノリバタリアン(技術自由放任派)の懸念、天才ハッカーの着想、自己拡散型スパムのマシンのっとり…。「いたちごっこ」と片付けられがちな攻防について、規範、法、経済、そして技術への深甚な影響を、体温を感じるように知ることができる。
このドラマは、「スパムの歴史はコンピュータネットワーク上に集まる人々の歴史の裏返し」であるとの本書の主張を反映するものでもある。なぜなら、スパムの計略は人々を標的とする以上、人間の注目が集積する「コミュニティ」の価値の裏返しとして定義されるからだ。
メディアとスパム
コミュニティの価値の裏返しである以上、スパムの歴史は私たちに以下のような自省を促す。「いったいわれわれはここで、スパムを抑制し罰しなければならないほどの、スパム以外のどんなことをしているのか」。私がシェアした猫やアルパカの写真は、排除されたスパムよりも有意義なのだろうか。アイドルのゴシップを延々とやりとりする対価として、どれほどのコストがかけられているのだろう?
スパムから想起される疑問は、さらにコンテンツの質にも及ぶ。昨今ではSNSにおいて友人の投稿と混じって表示される広告をスパムと感じることが多いかもしれない。他方で、煩わしいネイティブアドやバイラルメディアのなかにも、社会の本質をえぐり取り、新しい可能性を示唆するものも見受けられる。また、検索エンジンのアルゴリズムをすり抜けるために、生身の人間が大量のコンテンツを零細な対価で製作してスパムサイトを生み出しているが、そうしたコンテンツ・ファームと一般のメディアで行われるキャンペーン報道は、「注目の搾取」という文脈において、どのくらい差があるのだろうか。
もちろん、いかなるコンテンツも注目を獲得しなければ受け手に届かない以上、集積された注目を利用するという側面を有する。
そして、技術の不確実性やコミュニティの輪郭の曖昧さは、ジョナサン・ジットレインのいうところの生成性(generativity)の源泉であり、犯罪者にとっても、イノベーションを目指す人々にとっても、等しく恩恵を与える。スパムは不確定性という自由な隙間に生じるのであり、だからこそ、摩擦のなかで、生き延び、栄えたのだ。
本書では、
注目の搾取によって成り立つ公共性
しかし、ニュースメディアが、加熱した空気を沈静化させ、逆に空気が冷え切っていたら重要性を訴えて火をつけるような「空気の温度を調整するエアコンディショナー」(津田大介氏のメルマガ『メディアの現場』でのジャーナリスト、故・竹田圭吾氏の発言)を目指すとするならば、むしろ、スパムのように注目を積極的に「搾取」するような介入が必要かもしれない。
ヤフーニューストピックス編集部では、多くの人が知りたいと思っている社会的関心事(スポーツやエンターテイメントなど)だけでなく、公共性もトピックスの選択指標にしており、アクセスが伸びなくても公共性が高い情報(政治経済や国際社会など)を取り上げているとしている(ハフィントンポスト・ブログの記事「ネットニュースの世界に「公共性」は存在し得るか」における伊藤儀雄氏の発言より)。しかも、政治経済や国際社会のニュースが最初に目に付く上部に、芸能ニュースなどやわらかい話題を下部に配置しているという(「 Yahoo!ニュースはどうやってできているの?」での同氏の発言より)。
これは、行動経済学の知見に基づき、初期値や選択肢などを適切に設計することで、妥当な選択を促すというナッジ(Nudge)の一種として機能しているとみることができるだろう。「ヒジで軽く相手をつつくように」、行動を促す技術である。(なお、ヤフーと国立情報学研究所による共同調査によれば、ニュース見出しを閲覧するだけでも、政治知識の学習に効果的であるとされている。)
ところで、コンピュータ・
本書を監修した生貝直人氏・成原慧氏が指摘するように、「『人間の注目を搾取する』ものとして認識され、変化しつづけるスパムの概念に飲み込まれることを避けられなければ、人々はそのプラットフォームから徐々に離反し、インターネットを形作る支配的なアーキテクチャは、またその姿を変えていくことになる」からである。すなわち、ジャーナリズムとして崇高な理念を実践し、社会全体の公共性を担保するものであったとしても、それがユーザーに受容されなければ、「おせっかい」「目障り」にすぎない。結局は、淘汰の憂き目にあう。
いま、ジャーナリズムやメディアだけでなく、数多くの事業者が身を削って、(おそらく各種のデータを頼りに)試行錯誤を繰り返している。メディアの大半が、対価として「注目」を支払うというビジネスモデルを採る以上、人々の邪魔をしないような絶妙なバランスを誰もが探らねばならない。スパムとの境界を知るために本書で歴史を学ぶことは、有効なメディアとは何かという仮説づくりの一助となるのではないだろうか。
【イベントのご案内】
本稿の執筆者である工藤郁子さんと、この記事でとりあげた『メディアと自民党』の著者・西田亮介さん、そして本誌編集発行人の仲俣が登壇するトークイベント「政治批評の再考ーー2016年の参院選とメディア、言論を展望する」が今週木曜日に東京・下北沢の本屋B&Bで開催されます。
日時:1月28日(木)20:00~22:00 (19:30開場)
場所:本屋B&B(世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F)
出演 :西田亮介(東京工業大学大学准教授)、工藤郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)、仲俣暁生(フリー編集者/文筆家。「マガジン航」)
※イベントの詳細はこちらをご覧ください。
http://bookandbeer.com/event/20160128_bt/
執筆者紹介
- 慶應義塾大学SFC研究所上席所員、マカイラ株式会社コンサルタント。
1985年東京都生まれ。オンライン署名プラットフォームを運営する Change.org, Inc.、戦略コミュニケーション・コンサルティング会社のフライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社を経て現職。専門は情報政策と広報。共著に『ソーシャルメディア論 つながりを再設計する』(青弓社)、論文に「共同規制とキャンペーンに関する考察」(情報ネットワーク・ローレビュー第13巻第1号)、「情報社会における民主主義の新しい形としての『キャンペーン』」(法学セミナー2014年1月号)など。
最近投稿された記事
- 2016.01.25書評メディアは(常に)スパムか?
- 2015.11.05書評政治参加の多様性とメディア